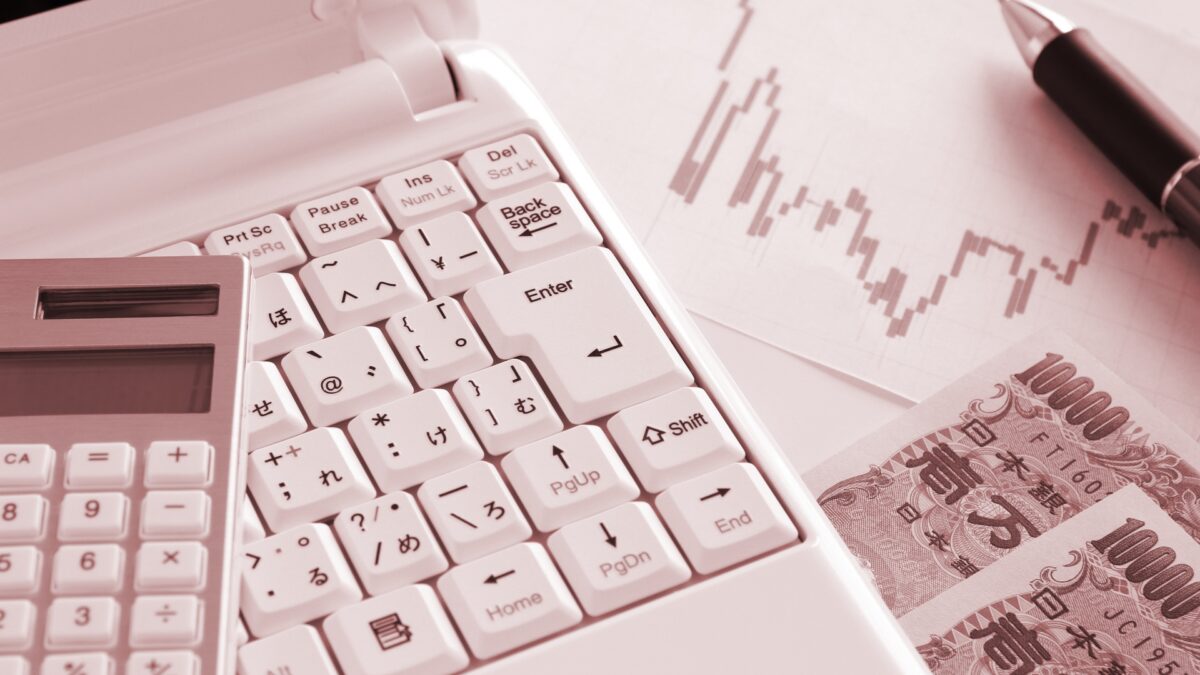コンサルタントを志望する多くの人にとって、避けては通れないのが「ケース面接」です。その中でも特に難易度が高いとされるのが、官公庁や自治体をクライアントとする公共セクターのケースです。なぜなら、企業コンサルティングとは異なり、目指すべきゴールが「利益の最大化」ではなく「公益の最大化」であるからです。
例えば、待機児童の解消や地域活性化、エネルギー政策、防災対策といったテーマでは、単に数字を動かすだけでは不十分です。多様なステークホルダーの利害を調整し、社会全体に受け入れられる納得解を導き出すことが求められます。こうした課題は、民間企業のケース以上に複雑で、長期的な視点や制度・法律への理解も欠かせません。
実際に、日本政府が民間コンサルティングファームへ委託する案件総額は2020年度に約1,705億円、翌2021年度も1,485億円と高い水準を維持しており、公共分野の需要は年々拡大しています。つまり、この分野に強い人材は今後ますます求められるということです。
しかし、公共セクターケースに初めて挑む人の多くは、「民間企業のフレームワークをそのまま当てはめてしまう」「実現不可能な理想論を述べてしまう」といった落とし穴にはまります。そこで本記事では、公共セクターケースの全体像から、実際の解法フレームワーク、さらに面接官が注目する評価ポイントまでを網羅的に解説します。
この記事を読み終えるころには、あなたは単なる“答えを出す候補者”から、「社会課題を解決するパートナーになれる人材」として一歩リードできる準備が整うでしょう。
公共セクターコンサルティングとは?その役割と重要性

公共セクターコンサルティングとは、官公庁や地方自治体、独立行政法人などの公共機関をクライアントとし、社会課題の解決や行政サービスの改善を支援するコンサルティング業務を指します。民間企業を対象としたコンサルティングと比べて、利益追求よりも国民全体の利益や社会的価値の最大化が目的になる点が大きな特徴です。
特に日本では、少子高齢化、地域格差、気候変動、防災対策といった課題が山積しており、それに対応する政策や施策を実行するために、外部の専門家であるコンサルタントの役割がますます重要視されています。近年、公共機関がコンサルティングファームへ委託する金額は増加傾向にあり、2020年度には1,700億円を超える規模に達しています。これは、行政だけでは解決が難しい複雑な問題が増えていることを示しています。
公共セクターコンサルタントが関与するテーマには以下のようなものがあります。
- 医療や介護の制度改革
- 教育格差やデジタル教育の推進
- 地方創生や観光振興
- エネルギー・環境政策
- 災害対策やインフラ整備
これらのプロジェクトは、単なる業務効率化にとどまらず、国民生活に直結するため、成果が社会全体に与える影響は極めて大きいです。したがって、公共セクターのコンサルティングには高度な分析力や論理的思考力に加えて、制度や法律、政策の知識が求められます。
また、民間企業のように株主や顧客だけでなく、国民、地方自治体、NPOなど複数のステークホルダーに配慮する必要がある点も特徴です。合意形成力やファシリテーション力が不可欠であり、単に「答えを出す」だけではなく「納得できるプロセスを設計する力」が評価されます。
公共セクターコンサルタントは、社会をより良くするための変革を推進する立場であり、日本の未来を形作る存在と言っても過言ではありません。この役割を理解することが、ケース面接に臨む第一歩となります。
民間企業ケースとの違いを理解することが合格への第一歩
公共セクターケースと民間企業ケースは、一見すると似たような課題解決のプロセスを踏むように思われますが、その本質は大きく異なります。最も大きな違いは、解決のゴール設定にあります。民間の場合は「利益の最大化」が中心ですが、公共の場合は「公益の最大化」が目的となります。
この違いを整理すると次のようになります。
| 項目 | 民間企業ケース | 公共セクターケース |
|---|---|---|
| ゴール | 利益や売上の最大化 | 国民や地域社会の利益の最大化 |
| 利害関係者 | 株主・顧客・社員 | 国民・行政・地域団体・NPOなど |
| 制約条件 | 市場競争やコスト構造 | 法制度・予算制約・政治的合意 |
| 成果の測定 | 財務指標(売上、利益率など) | 社会的指標(雇用創出、福祉向上など) |
このように、公共セクターでは経済的合理性だけでなく、社会的公正や公平性、実現可能性が強く重視されます。例えば待機児童問題をテーマとしたケースでは、「保育施設を増やす」という解決策を示すだけでは不十分です。財源の確保、地域の受け入れ体制、制度上の規制など、複数の要素を考慮しなければ現実的な提案にはなりません。
また、公共セクターケースは「唯一の正解」が存在しないのも特徴です。複数の解決策の中から、実現可能性や合意形成のしやすさを含めて総合的に評価されるため、面接官は論理展開の筋道やステークホルダーへの配慮を注視します。
公共セクターケース面接で合格するためには、民間企業ケースの延長線上で考えるのではなく、「公益」という軸を常に意識し、現実的でバランスの取れた解答を示すことが不可欠です。この意識の有無が、面接官に「公共案件を任せられる人材かどうか」を判断させる決定的なポイントとなります。
公共セクターケースに挑むための思考フレームワーク

公共セクターケース面接では、課題の本質を正しく捉え、複数の制約条件を踏まえて現実的な解決策を提示することが求められます。そのためには、論理的思考を補助するフレームワークを活用することが効果的です。
代表的なフレームワークとしては以下が挙げられます。
- MECE(漏れなくダブりなく)の視点で課題を整理する
- ロジックツリーを用いて原因と施策を分解する
- SWOT分析で強み・弱み・機会・脅威を評価する
- ステークホルダー分析で利害関係を整理する
- コストベネフィット分析で費用対効果を検討する
これらを組み合わせることで、解答の説得力と現実性を高めることができます。
MECEとロジックツリーの活用
公共課題は複雑に見えますが、MECEの考え方を使うことで構造的に整理できます。例えば「地方の人口減少」をテーマにする場合、人口流出の要因を「雇用機会」「教育環境」「インフラ整備」「地域魅力度」といった要素に分解できます。さらにロジックツリーを使って、それぞれの要素がどういう要因から成り立っているのかを深掘りすることで、抜け漏れのない分析が可能になります。
ステークホルダー分析の重要性
公共案件は、国民、自治体、企業、市民団体など多様な関係者が存在します。そのため、解決策を提示する際には「誰にどのような影響があるか」を明確に示す必要があります。例えば、再生可能エネルギー導入を議論する場合、発電事業者、住民、地方自治体、環境団体といったステークホルダーの利害を調整するプロセスを示すことが重要です。
コストベネフィット分析の応用
財源が限られる公共セクターでは、施策の費用対効果を数字で示すことが評価につながります。政策提言において「年間コストは数十億円だが、雇用創出や税収増により数百億円の社会的リターンが期待できる」といった具体的な比較を行えば、現実的で実行可能な施策として説得力を持ちます。
フレームワークは万能ではなく、状況に応じて組み合わせて使う柔軟さが求められます。重要なのは、形式にこだわることではなく、課題解決の筋道を相手に納得感を持って伝えることです。
代表的なケーステーマと解答アプローチの実例
公共セクターケース面接では、日本社会の課題を題材にしたテーマが頻出します。典型的なテーマと、それに対するアプローチ例を見ていきましょう。
少子高齢化への対応
日本の65歳以上人口は2022年時点で全人口の29%を超えており、世界でも類を見ない高齢社会に突入しています。このテーマでは、医療・介護制度の持続可能性や労働力不足が課題として設定されることが多いです。
解答アプローチの例としては、
- 高齢者の就労促進
- 医療のデジタル化による効率化
- 外国人労働者の受け入れ拡大
といった施策を組み合わせ、費用対効果や社会的受容性を考慮して提示します。
地方創生と人口減少対策
地方都市の人口減少は深刻で、総務省の統計によれば2040年までに896の自治体が消滅可能性都市とされています。このケースでは「地域に若者を定着させるための政策」を問われることがあります。
アプローチ例としては、
- 地方移住支援金制度の拡充
- リモートワーク推進による都市部人材の流入
- 観光資源の活用と地域ブランド化
といった施策を、財政的持続性や地域ごとの特性を踏まえて検討します。
災害対策とレジリエンス強化
日本は自然災害が多い国であり、地震、台風、水害などをテーマとしたケースも頻出です。ここでは「限られた予算で防災インフラをどう整備するか」といった課題が出されます。
この場合は、被害規模や発生確率を踏まえて投資の優先順位を決める「リスクベースアプローチ」を活用することが有効です。さらに、自治体間の連携や住民参加型の防災計画を盛り込むと現実的な提案になります。
教育格差の是正
OECDの調査によると、日本では家庭の経済状況が子どもの学力に強く影響する傾向が報告されています。このテーマでは「教育格差を縮小する政策」が問われます。
解答例としては、
- 給付型奨学金の拡充
- オンライン教育の活用
- 教員の研修強化と地域間格差の是正
などを提案し、予算配分や効果検証の仕組みをセットで示すことがポイントです。
ケース面接で高く評価されるのは「課題に多面的にアプローチし、社会的インパクトと実現可能性を両立させる解答」です。具体的な施策と数字を組み合わせながら、全体像を論理的に描く力が求められます。
面接官が重視する評価ポイントと求められる資質

公共セクターのケース面接では、論理的な回答を提示するだけでなく、面接官が重視する資質を理解し、適切にアピールすることが不可欠です。評価ポイントを把握して対策を行うことで、面接突破の可能性は大きく高まります。
論理的思考力と構造化力
公共課題は複雑で、解答には多角的な視点が求められます。面接官は、受験者が課題を適切に分解し、筋道立てて解答を導けるかを注視しています。例えば、教育格差の是正について問われた場合、単に「奨学金を増やす」と答えるのではなく、「家庭環境・地域資源・制度的支援」の3つの視点で整理した上で提案することが評価されます。
実現可能性と現実感
公共案件では理想論ではなく、限られた予算や制度上の制約を踏まえた現実的な解答が重要です。例えば、防災施策の提案では「全国一律に防潮堤を設置する」といった非現実的な案は避けられ、被害規模や発生頻度を考慮した優先順位付けが求められます。
コミュニケーション力と合意形成力
公共セクターは多様なステークホルダーを巻き込む必要があるため、解答の過程で「誰にどのような影響があるか」を意識して説明できる力が問われます。実際の現場でも、住民説明会や行政との協議を通じて合意形成を図ることが多いため、その適性を見られています。
公共への使命感
利益追求型の民間案件とは異なり、公共案件では「社会をより良くする」という強い動機が評価されます。面接官は、候補者が社会課題に真摯に向き合う姿勢を持っているかどうかを確認しようとします。
公共セクターのケース面接では、論理的な分析力に加えて、実現可能性と公共への使命感を兼ね備えていることが高評価につながります。このバランスを意識することが、選考突破の決め手になります。
よくある失敗例とその回避策
公共セクターケース面接で多くの受験者が陥る失敗には一定のパターンがあります。それを事前に理解し、回避する準備をすることで、回答の完成度を大きく高めることができます。
民間型の思考に偏る
典型的な失敗は、公共案件を民間案件と同じように「利益最大化」で考えてしまうことです。例えば、待機児童問題を「保育園の収益性」からのみ論じてしまうと、公益性や社会的影響への視点が欠けてしまいます。公共案件では「誰がどのように恩恵を受けるのか」を意識する必要があります。
実現不可能な理想論
「すべての地域に大学を設置する」「全国一律で同水準の医療体制を整備する」といった非現実的な解答もよくある失敗です。予算、法制度、人的資源などの制約を無視した提案は説得力を欠きます。回避策としては、具体的な優先順位を示し、段階的に実現可能な施策を提案することが重要です。
データや根拠の欠如
漠然とした提案を繰り返すと、説得力が弱くなります。公共セクターでは統計や調査データが豊富に存在するため、信頼性のある数字を根拠として組み込むことが有効です。例えば、「高齢化率は29%を超えており、医療需要は今後さらに増加するため、医療デジタル化が急務です」といった形で提示すると具体性が増します。
時間配分のミス
ケース面接は限られた時間内で解答をまとめる必要があるため、序盤の分析に時間をかけすぎて結論が曖昧になることも失敗の一因です。回避策としては、最初に仮説を立て、それを検証するプロセスを意識することで、効率的に回答を組み立てることができます。
失敗を防ぐ最大のポイントは、公共セクターの特性を理解し、データに基づいた現実的かつ公益性の高い解答を提示することです。準備段階で典型的な誤りを把握しておけば、面接本番で冷静に対応できるでしょう。
日本の社会課題を題材にしたケーススタディ
公共セクターのケース面接では、日本特有の社会課題がテーマとして出題されることが多くあります。少子高齢化、地域活性化、エネルギー政策、防災、教育格差など、国の将来を左右するテーマが中心です。ここでは代表的な事例を取り上げ、実際にどのような思考プロセスで解答を構築すべきかを解説します。
少子高齢化と労働力不足
日本は世界でも最速で高齢化が進む国の一つです。総務省の統計によれば、65歳以上の人口比率は2022年時点で29%を超え、労働人口の減少が顕著になっています。このテーマでは、労働力不足への対策が問われることが多いです。
アプローチ例としては、
- 高齢者の再雇用制度を拡充する
- DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務効率化を推進する
- 外国人労働者の受け入れ枠を柔軟化する
といった施策が考えられます。これらを財政負担、社会的受容性、制度改正の可能性といった観点で比較し、優先順位をつけることで現実性のある提案ができます。
地方創生と人口流出
地方の過疎化は深刻な課題で、国立社会保障・人口問題研究所の予測では、2045年までに多くの自治体が人口半減に直面するとされています。このテーマでは、地域活性化や若者定住策が焦点になります。
考えられる施策としては、
- リモートワーク環境を整備し都市人材を誘致する
- 観光資源を活用して地域ブランドを確立する
- 地方大学や専門学校と産業を連携させて人材循環を促進する
といったアプローチがあります。重要なのは、地域ごとの特性に応じたカスタマイズを前提にすることです。
エネルギーと環境政策
カーボンニュートラル実現に向け、再生可能エネルギーの普及は公共課題として頻繁に扱われます。ケース面接では「コスト負担と環境効果を両立する政策設計」が問われることが多いです。
たとえば、
- 太陽光発電や風力発電の導入補助
- 蓄電システムの普及促進
- 地域マイクログリッドの活用
などを比較検討し、短期的・長期的な効果を評価することで説得力のある解答につながります。
防災とインフラ強靭化
日本は自然災害が多く、地震や洪水をテーマとしたケースも多く出題されます。ここでは「限られた予算でどの地域に優先的に投資すべきか」が鍵となります。統計データや過去の被害額を活用して、リスクベースで判断する姿勢が評価されます。
教育格差の是正
経済的背景による学力差は長年の課題であり、OECDの調査でも日本は親の所得と子どもの学力の相関が強いと報告されています。このケースでは、奨学金制度の充実やオンライン教育の活用が代表的な解答になります。
日本の社会課題を扱うケーススタディでは、社会的影響と実現可能性の両立をいかに説明できるかが合否を分けるポイントです。面接官は「理想と現実を橋渡しできる人材」を求めているため、統計や事例を根拠にした具体的な提案を行うことが重要です。